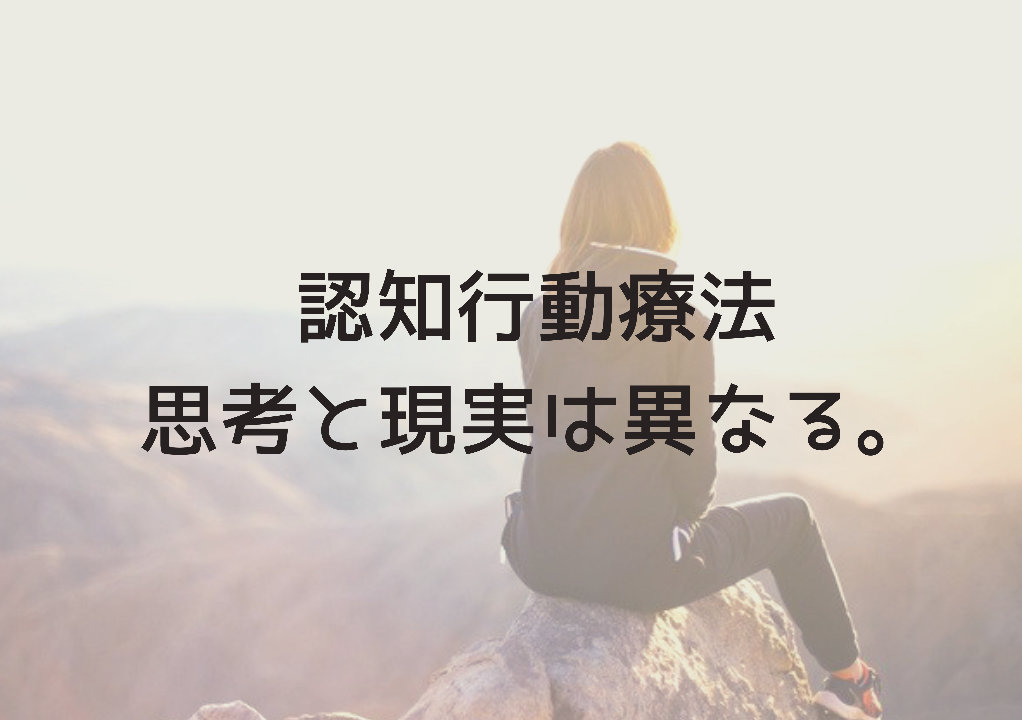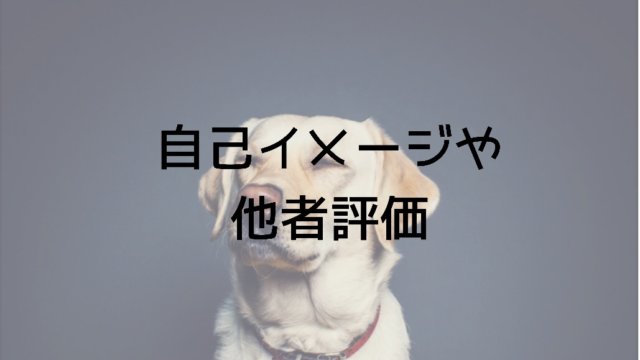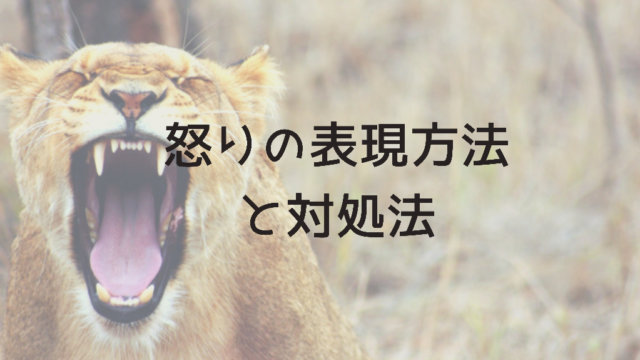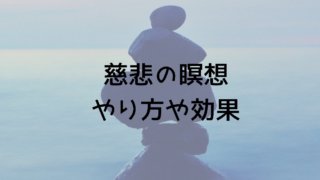みなさん、こんばんは。
臨床心理士のゆり(@counseler_yuri)です。
本日は、「思考と現実は異なる」という点についてまとめたいと思います。
認知行動療法では、思考と現実は分けて考えます。言葉にすると当たり前ですが、特にストレスが強い状況だと、思考と現実が混ざり合ってしまうことがあります。
例えば、実際に相手が言ったセリフなのか、相手が言ったように自分が考えた(感じた)のか、実は記憶が曖昧になっている場合もあります。
認知行動療法では事実と思考を区別する
認知行動療法でモニタリングをしてもらうときに、「考え」にカギカッコをつけてもらつのは、事実と思考を区別するため。
考えは考えにすぎない。自分の頭の中の世界。
でも、時に現実かのように感じたり、思い込んでしまう。
考えは考えにすぎない。必ずしも現実ではない。
— 心理カウンセラーゆり⭐︎(臨床心理士/公認心理師) (@counselor_yuri) July 26, 2019
認知行動療法でモニタリングをするときは、「考え」にカギカッコをつけます。
これは事実と思考を区別するためです。
考えは考えにすぎない。自分の頭の中のものです。必ずしも現実ではありません。
でも、時に現実かのように感じたり、思い込んでしまいます。
モニタリングは、どんな状況でどんな考えが浮かび、どんな感情を感じたか、自己観察し、メモすること。
私たちは世界を意味づけしている
私たちは世界を意味づけしている
同じ状況でもストレスに思う人と思わない人がいる。
私たちは、光合成みたいに、環境から直接作用を受けて反応して生きている訳ではない。
環境に対して、「今日の太陽は暖かいな」「暑すぎて溶けてしまう」と自分たちがどう捉えるかで、意味づけが変わってくる。
— 心理カウンセラーゆり⭐️(臨床心理士/公認心理師) (@counselor_yuri) August 2, 2019
出来事と結果の間には「考え」が挟まっています。
目の前にケーキがあって(出来事)、「美味しそう」と考えたから、食べました(結果)。出来事と結果が直結しているわけではなくて、間にどう考えたかによって結果が変わります。
例えば、目の前にケーキがあって(出来事)、「太りそう」と考えたら、食べなかったかもしれません(結果)。
つまり、私たちは世界を意味づけしています。
同じ状況でもストレスに思う人と思わない人がいます。それは、同じ状況に対してどう考えたかで、どのくらいストレスを感じるかどうか結果が変わってくるからです。
私たちは、光合成みたいに、環境から直接作用を受け、反応して生きている訳ではないです。
日が射してる状況に対して、「今日の太陽は暖かいな」「暑すぎて溶けてしまう」と自分たちがどう捉えるかで、意味づけが変わってきます。
自分の価値観や、マイルール、癖など
自分の価値観や、マイルール、癖など、世界の意味づけに影響する。
・ネガティブ
・ポジティブ
・被害的
・自責的そのひとによって、どんな意味づけをしやすいかは異なる。
それは、つまり、
自分が変われば、世界の意味づけも変わってくる。— 心理カウンセラーゆり⭐️(臨床心理士/公認心理師) (@counselor_yuri) August 2, 2019
私たちが世界を認知するとき、それぞれの価値観や、マイルール、考え方の癖などが影響します。
・ネガティブ
・ポジティブ
・被害的
・自責的
そのひとによって、どんな意味づけをしやすいかは異なります。
私たちは、環境の影響を直接受けていると考えやすいです。
でも、必ず環境と自分の反応の間には、
「どう世界を意味づけたか」
という認知の部分が加わる。
そして、私たちの反応は、認知の影響をものすごく受ける。
— 心理カウンセラーゆり⭐️(臨床心理士/公認心理師) (@counselor_yuri) August 2, 2019
私たちは、環境の影響を直接受けていると考えやすいです。
でも、必ず環境(状況)と自分の反応(結果)の間には、
「どう世界を意味づけたか」
という認知の部分が加わります。
そして、私たちの反応は、認知の影響をものすごく受けます。
それは、つまり、自分のパターンや癖に気づき、
少しでも変化があれば、世界の意味づけも変わってくるということです。
この認知のパターンを、完全に変えることは難しいし、目指すところではありません。パターンを知り、別のパターンがないかなと可能性を探り、選択肢を増やしていきます。
考えの柔軟性を高める、考えの幅を広めるイメージです。
そうすると、私たちの反応部分が変化するという仕組みです。